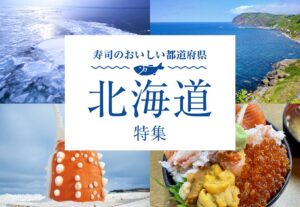かんたん!寿司の握り方2-仕込みを始めよう

寿司を自分で握るには長い期間の修業が必要だと思っていたりしませんか?
たしかに、寿司屋の職人は魚の捌き方から酢飯の合わせ方まで、厳しい鍛錬を積み重ねて身につけていきます。でも、プロの職人と同じレベルまでいかなくても、実はコツさえ押さえれば、一般の家庭でも美味しい寿司を作ることができるんです。
「寿司の握り方・道具編」に引き続き、今回は、寿司を握る上で大事な「仕込み」のコツをご紹介します。寿司は材料がシンプルな分、仕込み一つで味が大きく変わってしまいます。ポイントを押さえて自宅でプロにも負けない美味しい寿司を作ってみましょう!
シャリを合わせる

まず始めに、シャリ作りの材料と合わせ酢を作る時のちょっとしたコツを紹介します。
寿司はシャリによって味が変わってくると言っても過言ではありません。
合わせ酢の黄金比をしっかり覚えましょう!
材料
1.米(お好みの量)
~合わせ酢(4人前)~
2.米酢(白ワインビネガーでも可) 80g
3.砂糖 40g
4.塩 20g
5.煮切り酒 10g
6.煮切りみりん 2g
※合わせ酢の黄金比率「米酢:砂糖:塩=4:2:1」
5、6の煮切り酒とみりんを用意するのが大変だという人は入れなくても大丈夫ですよ
合わせ酢を作る
用意した材料を鍋に入れて火にかけます。
砂糖、塩が溶けた時点で完成です。火から外して冷ましましょう。砂糖と塩が酢に対して多いように感じるかもしれませんが、火にかければ溶けてしまうので安心してください。
合わせ酢は冷蔵庫で保存できます。少し多めに作って次回にとっておくのも良いかもしれませんね。
米を炊く
次にお米を炊きましょう。普段使っている家庭用炊飯器で問題ありません。
ここで注意したいのは水の量。白米を炊く時の水のラインから2mmほど下に調整します。水の分量を少し減らす事で、後に合わせ酢を混ぜた時に米がベチャベチャしなくなります。炊き終わったら30分ほど蒸らすことも忘れずに!
シャリを合わせる
炊きあがった白米を広めのバットに移します。
白米を移すには、飯台と呼ばれるシャリ用の桶を使うのが理想ですが、広めのバットでもかまいません。ここで大事なのは、白米が熱いうちに合わせ酢を混ぜること。少しずつ合わせ酢をかけ、しゃもじで切るように混ぜていきます。合わせ酢は米一合に対して40gを目安にしてください。
合わせ酢を混ぜ終わったら、酢飯を団扇で扇いで冷まします。
ある程度混ぜ終わったら、濡れ布巾を上からかけて、乾燥させないようにするのがポイント。
ネタを切る

シャリができた後はネタの準備です。
ここでは既に捌いてある魚を扱う前提でお話しします。スーパーなどで好きな魚の切り身を買って準備してくださいね。
上身と節と柵の違い
魚の切り身にも種類があります。
三枚おろしにされた状態の「上身」、中骨を境にして切り分けた「節」、骨などが取り除かれ、スーパーでよく目にする「柵」があります。どの切り身も寿司ネタとして使うには骨の処理、適切な幅、高さに合わせなくてはなりません。
ネタの切り方
魚は基本的に柵から切ることになります。
柵には「長サク」と「手サク」があり、寿司ネタにちょうど好いのは「手サク」ですね。
手サクはあまり角度をつけずに切れますが、長サクの場合、高さが手サクより低く、包丁を倒して角度をつけながら切ることになります。
ここでのポイントは、柵に節目がある場合、基本的に節目と交差するように切る事。ネタの厚さは3mmを目安に切りましょう。
家庭で扱いやすいネタは?
家庭で扱いやすいネタは、「どこでも取り扱っている」「切りやすい柵になって売られている」魚です。これらの特徴を踏まえると、マグロとサーモンがおススメです。両方とも入手しやすく、切りやすい柵の形をしていることがほとんどです。ヒラメやタイなどの白身魚も柵で売られていますが、厚さがバラついているので包丁を使い慣れていない人にとっては難しいかもしれません。
ネタを扱う上で注意したいこと
生食なので、一度冷凍されているものが安全ですね。
切り付けが終わったネタは、いざ握るまでは冷蔵庫に入れるなど、常温に戻さないようにしましょう。スーパーで魚を買う時は、生食用かどうか確認することも大事です。
寿司の仕込みは誰でもできる!
寿司の味付けはシャリでほとんど決まってしまいます。
合わせ酢を作る際、材料の分量をしっかり守りましょう。それ以外は特に難しい仕込みはないので、ぜひ家庭でも寿司を楽しんでみてくださいね。