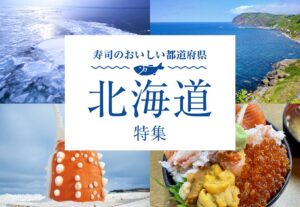かんたん!寿司の握り方3|5分でわかる魚の捌き方の基本

「自宅で寿司を握るなら、魚を捌くところからやってみたい!」という人のために、魚の捌き方をご紹介します。魚を捌くのは簡単ではありませんが、コツを掴んでしまえば大丈夫。
基本的な捌き方である「三枚おろし」さえ習得してしまえば、色んな魚を捌くことができます。魚を捌けるようになれば、魚を丸ごと買うこともできます。丸ごと買えば、寿司だけでなく、部位ごとに色々な料理に活用できてとってもお得ですよ!
寿司ネタ用の魚を捌く前に
まず始めに、魚を捌くのに必要な道具をご紹介します。
最初に用意するもの
1.俎板(まないた)
2.包丁
3.キッチンペーパー、または布巾
4.鱗取り用の道具
包丁はよく切れるものを準備しましょう。切れ味が悪いといくら練習しても綺麗に捌けるようになりません。
また、布巾を使う場合は、魚の匂いが付着しますので、捨てても構わないものを使うようにしてくださいね。
鱗取りの道具がない場合は、ペットボトルのキャップでも代用できます。家で鱗を取りたくない時は、魚屋さんに取って貰うようにお願いしましょう。
三枚おろしに向いている魚
三枚おろしの練習でよく使われ、寿司ネタにもなりやすい魚と言えば、「アジ」「スズキ」「タイ」が挙げられます。大き目のサイズの方が骨の位置が分かりやすく、包丁の動かし方を練習しやすいのですが、小さいサイズで練習の量を増やしてみるのも好いかもしれませんね。
魚を丸ごと買う時は、新鮮な魚を選びましょう。新鮮な魚は身が絞まっていて捌きやすく、寿司ネタにするにも適しています。鮮度の良い魚の見分け方は、「目が透き通っている」または「ドリップ(血)が出過ぎていないか」チェックするのがポイントです。
魚の捌き方(三枚おろし)
では、実際に三枚おろしの方法を見ていきましょう。
慎重になり過ぎてゆっくりやると、鮮度が悪くなってしまい、身が崩れやすくなってしまいます。思い切って捌くようにしましょう!
1.魚の鱗を取る
鱗を取る時は鱗が飛び散ってもいいように、シンクの中で行います。この際、蛇口から少し水を出して魚に当てながら作業すると、やりやすいです。
また、魚は滑りやすく、魚の尖っている部分で怪我をする可能性もあるので、軍手を嵌めてやるのがポイント。鱗取りである程度鱗を度取ったら、最後に包丁の先端部分を使って、取り落とした鱗がないか、最終確認しましょう。
2.魚の頭を落とす
まず始めに、片側ずつ魚のエラからヒレにかけて切り込みを入れます。
反対側に入れた時に最後まで包丁を入れきって頭を落とすイメージです。この時のポイントは、切り込みを入れる際、包丁を身の方に倒して斜めに入れると、無駄に身を残さずに切ることができます。
3.内臓を取り出す
頭を落としたら、腹に切り込みを入れ、内臓を取り出しましょう。
内臓を取り出したら、骨に沿ってさらに切り込みを入れ、血を洗い落としやすくします。竹串を合わせたようなものや専用の道具で腹を洗い、洗い終わったら、しっかりと魚の水気を取ります。内臓を取り出したら、次はいよいよ魚をおろしていくので、俎板を綺麗な状態にしておくのも忘れないでくださいね。
4.三枚に分ける
では、実際に魚を切り分けていきしょう。
最初に魚の頭を右側にし、腹を下に向けるように置きます。
腹から包丁を入れ、背骨と包丁の裏側に骨を感じながら尻尾の方へ引いていきます。
同じく頭を下にして、背中側も骨を感じながら引きます。尻尾の付け根の部分の少し下から垂直に包丁を入れ、一気に引きます。身と骨が離れたら、尻尾を切り離しましょう。
次は反対側にひっくり返して、背中から包丁を入れ、その後に腹に包丁を入れます。
手順はさきほど説明したのと逆になります。基本的に魚をおろす順番は、「腹背背腹」と言われ、魚を触る回数を極力少なくするのがポイント。
5.魚の骨を取る
腹骨は包丁を使って削ぐようにして切り落とします。
中骨はピンセットで抜いても構いませんが、面倒な場合は中骨を境にして二つの節にしてもいいでしょう。寿司ネタにする場合、ピンセットで抜くより節にした方がネタを切りやすくなりますね。
魚を捌けるようになるには練習が必要

いかがでしたか。上手に捌けましたか?
解説本を読んだり、画像や動画を見ると、魚を捌くのは簡単に出来そうに見えますが、実際やってみるとなかなか大変ですよね。
魚捌きは、何回も練習することで初めて「包丁で骨を感じる」感覚を掴めるようになります。
最初のうちは上手くいかないかもしれませんが、一回覚えてしまえばとても便利です。挫けずに練習してみてくださいね!